“がんばりすぎ”が招く身体のSOS
がんばることは、悪いことではありません。
誰かのために、何かのために、一生懸命でいたいと思うのは自然なことです。
でも、「がんばる」が無意識に「がんばりすぎ」になっているとき、
心は気づかなくても、身体が先に教えてくれることがあります。
「がんばりすぎ」が起こる背景
がんばりすぎてしまう人には、こんな共通点があることが多いです。
- 迷惑をかけたくない
- 甘えるのが苦手
- 失敗してはいけないと思っている
- 「ちゃんとしなきゃ」が口ぐせ
- 期待に応えないと自分には価値がないと感じている
これらの思いは、多くが子どもの頃の環境や親との関係に根ざしています。
「もっと頑張れば愛されるかも」
「迷惑をかけたら嫌われてしまうかも」
そんな無意識の不安が、今もがんばりすぎる原因になっていることもあります。
がんばりすぎが続くと、身体はどうなる?
心では「まだ大丈夫」と思っていても、身体の方が先に限界を超えてしまいます。
たとえば:
- 朝起きられない(身体がシャットダウンを始めている)
- 食欲が落ちる/過食になる(自律神経の乱れ)
- 呼吸が浅くなる、胸が苦しい(過度な緊張状態)
- 不眠、途中で何度も目が覚める(心が休めていない)
- 肌荒れや慢性的な便秘(ホルモンバランスの乱れ)
- 何をしても疲れが取れない(交感神経優位のまま)
これらは、身体からの“静かなSOS”。
決して怠けているのではなく、これ以上がんばらせないようにしてくれているのです。

身体のSOSを受け取ったとき、どうしたらいい?
1. 「ちゃんとしなきゃ」をゆるめてみる
まずは、自分にこんなふうに声をかけてあげてください。
「今日くらい、ちゃんとできなくてもいいよ」
「誰にも甘えられなかったね。少し休んでいいよ」
「ここまでよく頑張ってきたね」
“がんばってきた自分”を否定するのではなく、やさしく労う。
そこから、心も身体もほどけはじめます。
2. 小さな「やらない」を決めてみる
- 家事を完璧にやらない
- 返信をすぐ返さない
- 苦手な人と距離を置く
- 「NO」と言う練習をする
これは自分に主導権を取り戻すことでもあります。
「がんばらない選択」を少しずつ増やしてみましょう。
3. 身体の声を聞く時間をつくる
- 5分だけでも目を閉じて深呼吸
- 温かいお茶をゆっくり味わう
- 外を歩いて太陽の光を浴びる
- 疲れている日は湯船に浸かる
こんなささやかな習慣が、心と身体のつながりを取り戻す手助けになります。
がんばらなくても、整う力はもともと身体に備わっているからです。
「がんばらない」ことが、未来のがんばる力になる
「がんばらなきゃ」と思ってしまうのは、あなたがそれだけまっすぐで、やさしい人だからです。
でも、ずっとアクセルを踏み続けたままでは、どんなに強い車でも壊れてしまう。
ときにはブレーキを踏んだり、エンジンを止めて休むことも必要です。
がんばりすぎているとき、あなた自身が“自分の味方”でいてあげてください。

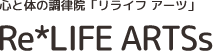

 ご予約
ご予約