なぜ薬では“根本解決”にならないのか?〜神経伝達と“回復力”の話〜
「薬を飲み続けているのに、なぜか良くならない…」
「いつまで飲み続けるの?」「本当はやめたい…」
そんな疑問や不安を抱えていませんか?
薬がまったく意味がないわけではありません。
ですが、症状が長引いたり繰り返してしまうのは、脳や神経の“根本的な働き”が回復していないことが背景にあります。
このブログでは、薬と神経の関係、そして回復力を取り戻すために必要な視点について、専門的な視点からお伝えします。
薬は“神経伝達の補助”であって“修復”ではない
抗不安薬や抗うつ薬、睡眠導入剤など、多くの薬は「神経伝達物質」の働きに関与しています。
たとえば:
- セロトニンの再取り込みを阻害する(SSRIなど)
- GABAの働きを強めてリラックスさせる(ベンゾジアゼピン系)
- ドーパミンやノルアドレナリンの分泌を促す
こうした薬の目的は、一時的に脳内の化学バランスを整えること。
つまり、「伝達」を助ける“補助輪”のような役割です。
ですが、神経細胞の回復や、脳の機能そのものを高める働きはありません。
薬だけでは「脳の疲労回復」や「機能のリセット」は起こらないのです。
神経がうまく働かなくなる3つの原因
薬が届くのは「表面の伝達」だけ。
その根っこには、次のような「神経機能の低下要因」があります。
1. 慢性的なストレス
ストレスが続くと、交感神経が過剰に働き、脳は常に“戦闘モード”。
これが神経回路の緊張・誤作動・過敏反応の原因に。
2. 栄養不足と炎症状態
脳の働きには、ビタミンB群・鉄・マグネシウム・タンパク質が欠かせません。
腸内環境の悪化や低血糖も、神経伝達の質を落とします。
3. 強い思い込みや自己否定
「私なんて…」「きっとダメだ…」という内的な思考パターンは、
脳内の回路を固定し、神経の柔軟な働きを妨げます。
神経の回復に必要なのは「生活」と「働きかけ」
神経の誤作動をリセットするには、“暮らし”と“刺激”が鍵です。
- 生活習慣の土台(睡眠・血糖・腸内環境・栄養補給)
- 呼吸・姿勢・リズム運動などの神経リハビリ
- 神経反射に基づくアプローチ(脳神経学的治療)
- 自分の内面と向き合う対話(カウンセリング・コーチング)
一見地味に見える取り組みの積み重ねが、神経の“可塑性(かそせい)”=回復力を引き出していきます。
薬を減らしたい人に必要なのは「段階」と「理解」
「薬をやめたい」「減らしたい」と思った時、焦りは禁物です。
- 自己判断での中断は、離脱症状や不調の再発につながることも
- 医師との相談や、服薬スケジュールの調整は不可欠です
- 減薬を目指すなら「整える順番」を知ることが大切です
まずは 脳と神経の状態を整える
→ 生活習慣・心の土台を安定させる
→ 主治医と相談しながら段階的に減薬していく
これが、失敗しないための自然なプロセスです。
薬に頼らないという選択に、確かな土台を。
「薬を飲みたくない」という気持ちは、
あなたの中に「本当の回復を目指したい」という意思がある証拠です。
当院では、
- 脳神経の機能を高めるアプローチ
- 栄養・生活習慣・心の癖の見直し
- 継続的に“自分を整える力”を養う支援
を通じて、「薬に頼らない身体と心づくり」をサポートしています。
症状に悩む毎日から、少しずつ自分の力を取り戻せる毎日へ。
一緒にその一歩を踏み出しませんか?

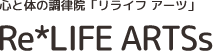

 ご予約
ご予約