“近すぎる”関係に疲れてしまうあなたへ── なぜ『優しすぎる自分』がしんどいのか
「いい人」でいることに、疲れていませんか?
✔ 頼まれると断れない
✔ 相手の気持ちを優先しすぎてしまう
✔ “察する”ことにエネルギーを使いすぎている
✔ 怒りや不満を飲み込んでしまう
✔ 一人になるとどっと疲れが出る
これらはすべて、「優しすぎる人」によく見られる特徴です。
しかしその優しさが、自分自身を消耗させているとしたら──
“人とつながる”ことがしんどいのは、あなたが悪いわけではありません。
それは、脳と心のパターンによって起きている“自動反応”かもしれません。

優しさの裏にある「恐れ」
「相手を傷つけたくない」「嫌われたくない」「迷惑をかけたくない」
こうした思いは、幼い頃に学んだ“関係性を保つための戦略”であることがあります。
幼少期に、親や周囲の大人からの愛情が不安定だったり、感情を自由に表現できなかったりすると、
「自分よりも相手を優先する」ことで、安全を確保しようとする傾向が脳にインプットされるのです。

脳と神経が覚えている「人の機嫌に敏感な自分」
このような対人戦略は、脳の“扁桃体”や“前頭葉”の働きとも関係しています。
- 扁桃体:危険や否定を察知し、ストレス反応を起こすセンサー
- 前頭葉:他者の気持ちを想像し、行動を調整するブレーキ役
人との関係に強い不安や過剰な気配りが働く人は、これらの脳領域が常に“緊張モード”にあります。
だからこそ、優しくしすぎたり、NOと言えなかったり、気をつかいすぎて疲れ切ってしまうのです。

“いい人疲れ”は心身症にもつながる
この過剰な対人緊張は、慢性的なストレスとなり、
- 頭痛
- 胃腸症状(過敏性腸症候群など)
- 慢性的な疲労感
- 自律神経の乱れ
- 抑うつやパニック発作
など、心と体の両方に症状を引き起こすこともあります。
回復には「脳に安心を再学習させる」ことが必要
優しすぎる自分を否定する必要はありません。
ただ、その優しさが“自分を犠牲にすることでしか成立しない”としたら、少し見直してみませんか?
当院では、「つい頑張りすぎてしまう」「自分を後回しにしてしまう」方に対し、
次のようなアプローチで脳と神経の回復をサポートしています。
当院のアプローチ
- 脳神経への調整アプローチ
→ 安全・安心を感じやすい神経状態をつくるケア - 身体面からのサポート(栄養・生活リズム)
→ 自律神経の働きを安定させるための習慣づくり - 心理的アプローチ(カウンセリング・コーチング)
→ 自分の本音や境界線に気づく対話のプロセス
「人に優しくしているのに、心が満たされない」
そんなときは、あなた自身の心の輪郭を取り戻すときかもしれません。

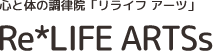

 ご予約
ご予約