心が疲れやすい人ほど知ってほしい、“栄養と神経”のつながり
「気持ちが不安定になるのは、心の問題だと思っていた」
「考えすぎだと言われても、止めらない」
そんなふうに、自分の心の弱さだと思い込んでしまうことがあります。
でも実際には、メンタルの揺れの多くが“栄養”と深く関係しています。
脳も神経も、栄養を材料にして働いています。
だから、どれだけ気持ちを前向きにしようとしても、
身体のほうが追いつけていないと、心は安定しづらくなります。

心の不調の背景で起きている“脳のエネルギー不足”
脳は全身の中で最もエネルギーを使う器官。
ただし、そのエネルギーは「気持ち」ではなく、栄養そのものから作られています。
必要な栄養が足りないと、脳は省エネモードに入り、
- 考えがまとまりにくい
- 落ち込みが強くなる
- やる気が湧かない
- 不安が大きくなる
といった“メンタルの乱れ”として表に出ます。
これは努力不足でも、心の弱さでもありません。
脳のエネルギーが足りない状態では、心のほうが耐えきれないのです。

栄養がメンタルを揺らす3つの仕組み
1. 神経伝達物質の材料が足りない
気持ちの落ち着き、意欲、集中、安心感――
これらを作っているのは、脳の中で働く神経伝達物質です。
たとえば
- セロトニン(安心感・睡眠の質)
- ドーパミン(やる気・集中力)
- GABA(不安を鎮める、リラックス)
これらはすべて、タンパク質・鉄・亜鉛・ビタミン類などの栄養を“材料”にして作られています。
材料が不足すると、作りたくても作れない。
その結果、気持ちが揺れやすくなります。
2. 血糖の乱れが“不安のスイッチ”を入れる
血糖値が急に下がると、身体は“危険”と判断し、
アドレナリンやコルチゾールといったストレスホルモンを出します。
これは身体を守るための反応ですが、同時に
- 不安
- 焦り
- 動悸
- イライラ
- 気持ちの落ち着かなさ
を引き起こしやすくなります。
「突然気分が不安定になる」
「夕方になると落ち込む」
そんな揺れには、血糖とホルモンの関係が影響していることが多いです。
3. 栄養不足は“神経の誤作動”を起こす
神経が正常に働くためには、ミネラル・脂質・ビタミンが必要です。
これらが不足すると、神経は小さなストレスにも過敏に反応しやすくなり、
人間関係の些細な一言にも心が揺れたり、
同じ不安をぐるぐる考えてしまったりします。
心ではなく、神経が疲れているサインです。
「考え方を変える」より前に、“働ける土台”を整える
落ち込む自分を責めても、
「頑張って気持ちを切り替える」ことはできません。
心を支えているのは、脳と神経。
その土台を作っているのが栄養です。
もしその土台が崩れていたら、
どれだけポジティブな考え方を学んでも、
一時的には変わっても、また元の不安に戻ってしまいます。
“心を変える努力”ではなく
“心が働ける環境を整える”こと。
そこが本当の回復の入り口です。

栄養 × 神経のアプローチで、心は静かに整っていく
ARTSsで大切にしているのは、
身体・脳・神経・栄養のつながりをひとつとして扱うこと。
- 朝がつらい
- 気持ちが乱れやすい
- 思考が止まらない
- 同じ疲れがずっと残る
こうした状態には、必ず“身体の理由”があります。
栄養で土台を整え、
神経の誤作動を調整し、
脳が働ける状態を作る。
その先で、気持ちは自然と軽く、静かに戻ってきます。

自分を責めなくていい
気持ちが安定しないことは、あなたの弱さではありません。
原因のない不調なんて、ひとつもないからです。
栄養は、心を支える“見えない土台”。
そこが満たされると、
あなた自身の本来の力が働き始めます。
心が揺れる日が続くときこそ、
身体と神経の声に耳を傾けてみてください。

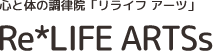

 ご予約
ご予約